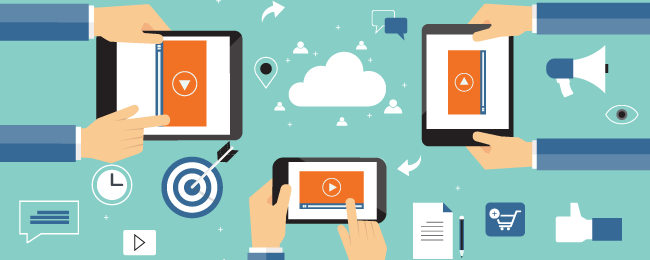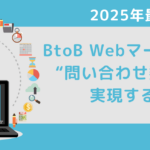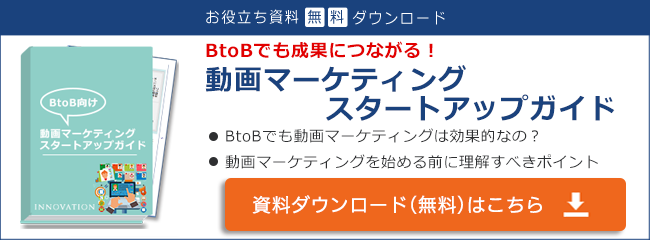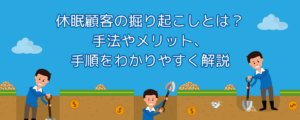動画コンテンツはBtoCマーケティングのみならず、BtoBマーケティングにも有効です。動画は、静止画と比較してユーザーに強い印象を残すため、マーケティングに活用する企業が増えています。
そこで今回は、BtoBマーケティングにおける動画コンテンツの種類からメリットやデメリット、マーケティングでの活用シーンまで詳しくご紹介します。
- ▼この記事でわかること
-
- BtoBマーケティングに動画が有効である理由
- BtoBマーケティングに動画を活用するメリットとデメリット
- BtoBマーケティングの動画活用シーン
- BtoBマーケティングでの動画活用を成功させるポイント
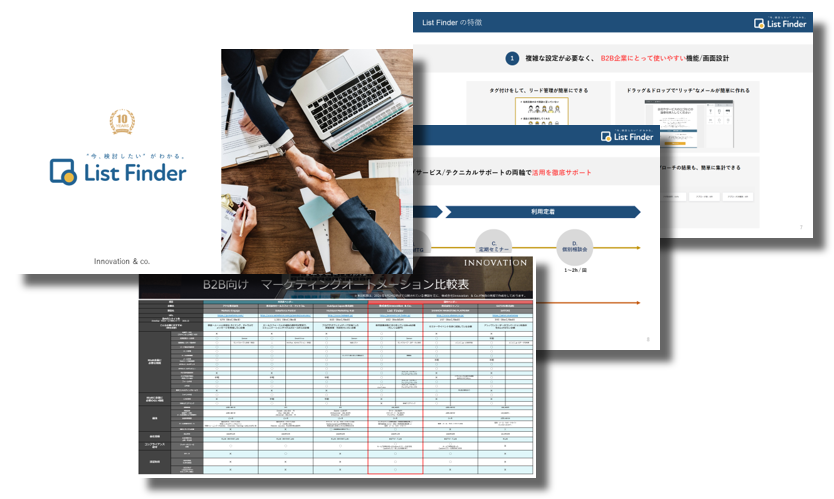
- マーケティングオートメーションツール
List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、手間のかかるマーケティング業務を効率化するための機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!
Contents
動画コンテンツはBtoBマーケティングにも有効?
動画コンテンツの活用はBtoC企業が先行しており、自社商品のプロモーション動画を自社サイトや動画サイト、SNSに投稿して集客活動を行っています。BtoCマーケティングでは、動画コンテンツで消費者の感情を揺さぶり、購買行動に向かわせることを目的としています。
ではBtoBマーケティングの場合はどうでしょうか?企業の担当者は常に何らかの課題・悩みを抱えており、問題解決につながる施策を見つけるべく、インターネットを利用した情報収集を日常的に行っています。
その際、より短時間で明瞭な情報収集を可能にしてくれるものの1つが動画コンテンツです。扱うべき情報量が増え続ける昨今、動画コンテンツはBtoBマーケティングにとっても欠かせない手段といえるでしょう。しかし、BtoBマーケティングでは商品購入の意思決定に複数の人間が関わり、購入検討に要する期間も長期に及ぶため、BtoCのような衝動買いは期待できません。
そのため、BtoBで活用される動画コンテンツは、自社と商品・サービスの認知度を高めて購入検討の対象に堅実にピックアップしてもらうこと、ターゲット顧客のニーズに寄り添ったメリットを提示して検討期間の加速を促すことなどが特に重要といえるでしょう。
BtoBマーケティングで動画の活用が注目されている背景
近年、BtoBマーケティングで動画コンテンツが注目されているのは、市場拡大と視聴環境の変化、そして意思決定者の行動変化が大きな要因です。YouTubeやLinkedInなどの動画プラットフォームが一般化したことで、企業担当者や意思決定者も動画を通じて情報収集を行う機会が増えています。
また、テキストよりも短時間で具体的なイメージを得られる動画は、製品理解や導入検討を効率化する手段として重視されています。さらに、リモートワークやデジタル営業の普及により、オンライン上で手軽に動画を視聴できる環境が整ったことも追い風となりました。
こうした要因が重なり、動画はBtoBマーケティングにおいて顧客接点を拡大し、購買プロセスを支援する有力なツールとして存在感を高めています。
BtoBマーケティングとBtoCマーケティングの違い
BtoBが法人向けのビジネスモデルであるのに対して、BtoCは、個人消費者を対象としており、成約に至るまでのプロセスが大きく異なるため、それぞれマーケティングの方法も異なります。
動画を効果的に活用するには、まずBtoBとBtoCマーケティングの特性を理解することが重要です。ここでは、両者の違いを見ていきましょう。
| BtoBマーケティング | BtoCマーケティング | |
|---|---|---|
| ターゲットの違い | 企業や法人が対象 | 一般消費者が対象 |
| 意思決定者の違い | 複数の関係者(経営者・担当者・購買部門など) | 主に個人(本人または家族) |
| 意思決定で重視される基準の違い | ROI(投資対効果)、コスト、導入後のサポート | 価格、デザイン、ブランド、感情的要素 |
| 検討期間の違い | 長期間(数カ月~数年) | 短期間(即決~数日) |
このように、BtoBマーケティングは理性的な判断と長期的な信頼構築が重視されるのに対し、BtoCマーケティングは感情的な訴求とスピード感が鍵となります。したがって、動画を活用する際も、BtoBでは「理解・信頼・共感」を促す構成を意識することが成果につながるでしょう。
BtoBマーケティングで動画を活用するメリットとデメリット
ここでは、BtoBマーケティングにおいて動画を活用することのメリットとデメリットを整理して解説します。
メリット
①短い時間で多くの情報を伝えられる
動画は視覚と聴覚を同時に刺激するため、短時間で効率的に情報を伝達できます。複雑な製品やサービスの説明も、アニメーションや実演を活用することで分かりやすく伝えられます。
たとえば、機械の操作方法やツールの機能紹介を動画にすることで、文章だけでは理解しにくいポイントも直感的に伝えられます。
②印象に残りやすい
動画は文章や画像よりも感情に訴えやすく、視覚的な記憶に残りやすい特徴があります。特にBtoBの場面では、製品の優位性や専門性を伝える映像が信頼感の向上につながります。
たとえば、導入事例や顧客インタビューを動画にすることで、実際の成功体験をリアルに伝えられ、視聴者に強い印象を与えます。
➂制作した動画は繰り返し活用できる
一度制作した動画は、Webサイト、SNS、プレゼンテーション、展示会などさまざまな場面で再利用可能です。これにより、長期的な費用対効果が高まります。特にBtoBビジネスでは、営業資料や製品デモ動画として活用できるため、営業担当者の負担を軽減しつつ、一貫した情報提供が可能になります。
また、動画を一部編集して短縮版を作成すれば、異なる用途やターゲットに応じた柔軟な運用ができ、マーケティング施策の幅を広げることができます。
④営業効率の向上
動画コンテンツを活用することで、営業担当者が顧客への基本説明に費やす時間を削減でき、商談の質を向上させることができます。
たとえば、製品紹介動画を事前に共有すれば、顧客は事前に情報を得た状態で商談に臨めるため、より具体的な提案が可能になります。また、動画はオンライン上で24時間活用できるため、営業機会の損失を防ぎつつ、担当者の負担を軽減できます。
⑤他社との差別化につながる
動画コンテンツを活用することで、競合と差別化しやすくなります。たとえば、製品の使用シーンを映像で伝えれば、機能や強みを直感的に理解してもらいやすくなります。
また、顧客の成功事例を動画で紹介することで、実績の可視化ができ、信頼性を高められるでしょう。さらに、企業の理念や価値観を映像で発信することで、ブランドの個性を打ち出し、他社との差別化を図ることが可能です。
デメリット
①制作コストがかかる
企業が動画を活用する際のデメリットの1つは、テキストコンテンツと比較して制作費用が高くなるという点です。特にクオリティの高い動画を制作しようとすると、高品質なカメラ、編集ソフト、ナレーション、アニメーションなどの費用が発生することも考えられます。
また、外部の制作会社に依頼する場合、企画・撮影・編集まで含めるとコストがさらに増大する可能性があります。コストを抑えるためには、簡単な動画は社内で制作する、テンプレートを活用するなどの工夫が必要になるでしょう。
②制作に時間がかかる
動画の企画、撮影、編集などの動画の制作には時間が必要になります。迅速なマーケティング活動を求められる場合、この点がハードルになることがあります。
特に、シナリオ作成や撮影準備に時間がかかると、短期間での情報発信が難しくなる場合があります。また、修正や調整が発生するとスケジュールがさらに伸びる可能性もあるため、計画的な進行が重要です。
➂不向きなコンテンツもある
動画は視覚的な訴求力が高い一方で、すべてのコンテンツに適しているわけではありません。たとえば、細かいデータや詳細な技術情報を伝えたい場合、動画では一部の情報が省略される可能性があり、テキストのほうが適している場合もあります。
また、視聴者が必要な情報をすぐに確認したい場合、長尺の動画では目的の部分にたどり着くのに時間がかかるため、情報の整理が必要です。
こうした点を考慮し、動画とテキストを組み合わせた情報提供が効果的です。
BtoBマーケティングに活用できる動画の種類
BtoBマーケティングにおいて動画コンテンツは、目的やターゲットに応じてさまざまな種類があります。適切な種類の動画を選ぶことで、ターゲットに対して効果的に情報を伝え、興味・関心を引き出すことが可能になります。
【1】商品紹介動画
テキストや画像だけでは伝わりにくい製品の特徴や使用イメージも、動画なら直感的に理解してもらえます。実際の利用シーンや導入前後の変化を映像で見せることで、製品の価値をよりリアルに訴求できます。
また、製造工程や活用事例を紹介すれば、技術力や信頼性を効果的に伝えられます。Webサイトや展示会で上映することで関心を引き、資料請求やホワイトペーパーのダウンロードなど次のアクションにもつなげやすくなる点がメリットです。
【2】会社紹介動画
特定の商品のプロモーションではなく、企業のイメージアップのために制作される動画です。企業イメージが売り上げに直結するBtoC企業でも、自社ブランディングには力を入れていますが、BtoBにおいても自社のパートナーとなる企業のイメージは重要なポイントです。
競合他社との差別化を図るためにも、企業ブランディングが欠かせません。企業ブランディング動画を通じて、会社に対する良いイメージを定着させましょう。
【3】セミナー動画
セミナーの様子を録画したものを動画として利用することも1つの方法です。近年ではWebとセミナーを合わせたオンラインセミナー「ウェビナー」も行われています。専門性の高い商品を扱うBtoBの場合、商品機能や活用事例を紹介するセミナーに参加したいと思うこともあるでしょう。
地理的な距離やコスト的、時間的な問題からセミナー会場に足を運べないときでも、Webを介することで、いつどこにいてもセミナーに参加することが可能なので、スケジュールが合わない多忙な見込み顧客や、遠隔地の見込み顧客の獲得にもつながります。
【4】インタビュー動画
自社で発信する商品情報は、あくまで商品を売る側から発信される情報であり、商品導入によって本当にメリットが得られるのかどうか不安を感じるユーザーは少なくありません。
そこで、実際に商品を購入したユーザーの導入事例を紹介することによって、その不安を払しょくすることがインタビュー動画の狙いです。商品導入前の不安や、導入後の効果をユーザーが直接語ることによって、リアリティを持ってユーザーに伝えることができ、商品の信頼性を高めることができます。
【5】広告・プロモーション動画
広告・プロモーション動画は、製品やサービスの魅力を訴求し、ターゲットに興味を持ってもらうことを目的としたコンテンツです。Web広告、SNS、展示会などで活用され、視覚的なインパクトを活かしてブランドの認知度を高めることができます。
特に、短時間で要点を伝えられる動画は、視聴者の関心を引きつけやすく、リード獲得や購買意欲の向上につながります。また、アニメーションや実写映像を組み合わせることで、ストーリー性を持たせ、より印象に残るコンテンツに仕上げることが可能です。
【6】リクルート動画(採用動画)
インターネットは現在の就職活動の必須ツールです。就活生はインターネットで情報収集した上で企業にエントリーするため、リクルート動画を制作して自社Webサイトや動画サイトに投稿する企業も増えています。
会社の事業内容やオフィスで社員が働く様子、若手社員が入社を決めた理由を取り上げ、動画を視聴した就活生は会社で働く自分の姿を描けるようになります。将来の働き方に不安を持つ女子就活生に向けて、産休育休の実績のある女性社員のインタビューを投稿するなども良いでしょう
目的別|BtoBマーケティングにおける動画の活用シーン6選
BtoBマーケティングにおける動画コンテンツは、多くの場面で幅広く応用できます。
1.リード獲得
動画を通じて、視聴者との信頼関係を築いていくことで、リード(見込み顧客)の獲得につなげることができます。具体的には、動画の視覚的なインパクトで視聴者の関心を引き付け、問い合わせフォームや資料請求のアクションを促します。
製品やサービスの紹介動画、課題を解決するソリューション動画などをLPやSNS広告に掲載することが効果的です。
2.認知の拡大
動画は、短時間で多くの情報を視覚的に伝えることで、企業やブランドの知名度を高めることができます。YouTubeなどに企業紹介動画を投稿することや、SNSでシェアされやすい短編動画を配信することで、ターゲット層にブランドを認識させることができます。
3.リード育成
動画は、すでに獲得したリードに対して追加情報を提供し、関心を深める手段としても活用されます。
たとえば、製品のデモ動画、導入事例動画、専門知識を解説するウェビナーのアーカイブ動画など、リードが持つ疑問や課題に応える動画を配信することで、興味関心を掻き立て、購買意欲を高めます。
4.成約率の向上
商談やクロージングの場面でも動画は重要な役割を果たします。たとえば、商談の際に個別の提案内容を動画で説明したり、自社の実績を示す動画を活用することで信頼感を構築することができるでしょう。
また、視覚的かつ感情に訴える表現で、購入の意思決定を後押しすることにもつながります。
5.社内外の教育活動
動画は、顧客や社内のメンバーに対する教育活動としても活用できます。たとえば、顧客向けの製品操作マニュアル動画や社内向けのeラーニング教材などで、説明書や口頭説明よりも理解が容易になり、反復利用することで教育効果を高めることができます。
6.採用活動
人材採用の場面でも動画は有効です。具体的には、企業文化を紹介するリクルート動画、社員インタビュー動画、会社説明会のアーカイブ動画などで、求職者に会社の雰囲気や価値観を視覚的に伝え、応募意欲を喚起します。
BtoBマーケティングにおける動画の効果的な配信チャネル
動画は、制作するだけでなく「どこで・どのように配信するか」で成果が大きく変わります。効果的な配信チャネルを選ぶことで、ターゲット企業の担当者に確実に情報を届け、リード獲得や商談化を促進できます。ここでは、主要な配信先での活用ポイントを紹介します。
自社サイトでの活用
自社サイトやランディングページに動画を掲載すると、訪問者の滞在時間や理解度が向上します。特に製品紹介や導入事例の動画は、ページ上部に配置することで訴求力を高め、問い合わせや資料請求率の向上につながります。
SNS広告での配信
LinkedInやYouTube、X(旧Twitter)などのSNS広告では、短尺動画で関心を引き、リード獲得を狙うのが効果的です。
冒頭3秒で「誰に・何を伝えるか」を明確にし、CTA(行動喚起)を設定することで、見込み顧客の次の行動につなげられます。
展示会・営業資料への組み込み
展示会ブースで動画を流すことで、来場者の目を引き、短時間で製品の魅力を伝えられます。また、営業資料や提案プレゼンに動画を組み込むことで、説明の属人化を防ぎ、誰が話しても一貫したメッセージを届けることが可能です。
BtoBマーケティングでの動画活用を成功させる4つのポイント
ここでは、動画コンテンツの活用を成功させるためにも意識しておきたいポイントを4つご紹介します。
1.ターゲットと目的を明確にしておく
動画制作の第一歩は、ターゲットと目的を明確にすることです。ターゲットが誰で、どのような課題やニーズを持っているのかを深く理解した上で、それに応える形で動画の内容を設計する必要があります。
また、「リード獲得」「認知拡大」「成約率向上」など、どの段階で動画を活用するのかを事前に決めておくことで、適切なメッセージを届けることができます。
2.意思決定に必要となる情報を入れる
BtoBの視聴者は、意思決定をするための具体的で信頼性のある情報を求めています。そのため、製品やサービスの特長や利点、競合との差別化ポイント、実績や導入事例など、相手の意思決定を後押しする情報を盛り込むことが重要です。
また、情報が一方的にならないよう、視聴者が「自分たちにどのようなメリットがあるか」を理解できる形で伝える工夫も必要です。
3.動画のクオリティを高める
動画は視覚と聴覚で情報を伝えるため、クオリティが低いと逆にブランドイメージを損なう恐れがあります。撮影の技術や編集のスキルが不足している場合、自社での制作を無理に行うのではなく、外部の専門業者に委託することを検討しましょう。
特に、製品デモや企業紹介など重要な用途で使用する動画は、プロの手によって洗練された仕上がりにすることで、視聴者に信頼感を与えることができます。
4.配信チャネルや活用シーンを事前に決めておく
動画の効果を最大化するためには、どの媒体で、どのようなシーンで活用するのかを事前に計画しておくことが重要です。
たとえば、リード獲得を狙うのであれば、SNSやランディングページが有効ですし、商談時には具体的な提案動画や導入事例動画が役立ちます。また、配信媒体ごとに最適な動画フォーマットや長さを考慮することも必要です。
このように、視聴者の行動や媒体の特性に合わせて配信計画を立てることで、効果的な動画活用が実現します。
動画コンテンツ制作の手順4ステップ
動画制作は、効果的なコンテンツを作成するために慎重な計画と実行が必要です。ここでは、動画制作の一般的な手順を紹介します。
1.目的・予算・納期の設定
動画制作の最初のステップは、目的・予算・納期を明確に設定することです。目的に応じて、動画のトーンや内容、配信場所などが決まります。たとえば、製品紹介動画なのか、企業のブランディング動画なのかによって、必要なリソースや制作時間が変わります。
また、予算の範囲内で可能な制作規模を確認し、納期を設定することで、全体的な進行がスムーズになるでしょう。この段階でしっかりと方向性を決めておくことが、制作の効率化につながります。
2.コンテンツ内容の企画
次に、動画のコンテンツ内容を企画します。この段階では、動画の目的に基づいて、どのような情報を伝え、どのような構成で動画を進めるかを決めます。たとえば、ストーリーボードを作成して動画の流れを視覚化したり、シナリオやナレーションの内容を作成したりします。
また、ターゲット視聴者のニーズや関心に合わせた内容を考慮し、メッセージを一貫して伝える方法を検討します。
3.素材集め・撮影
企画が固まったら、必要な素材を集め、撮影に入ります。素材集めには、既存の画像や動画を使う場合もあれば、オリジナルの映像やアニメーションを制作することもあります。撮影の場合は、場所や出演者を手配し、撮影計画を立てて、撮影の準備を整えます。
撮影では、画角や照明、音声などを調整し、最適な品質の素材を収集することが重要です。また、撮影時には、複数のシーンやアングルを撮影しておくと、後の編集で柔軟に使える素材が増えます。
4.編集
最後に、集めた素材をもとに編集作業を行います。編集では、シーンを切り替えたり、音楽やナレーションを追加したり、不要な部分を削除することで、動画のストーリー性を強化します。動画の尺を調整し、視覚的にも聴覚的にも一貫性が保たれるように仕上げることが大切です。
また、必要に応じてテキストやグラフィックを加え、視覚的にわかりやすくしたり、視聴者の注意を引きつけたりします。最終的には、色調整や音声の調整を行い、動画の完成度を高めていきましょう。
これらの手順を踏むことで、目的に合った効果的な動画コンテンツを制作することができます。
動画コンテンツの制作費用と内製・外注の選び方
動画の制作には、目的・内容・品質レベルによって費用が大きく変わります。ここでは、一般的な制作相場の目安と、内製・外注を判断する際のポイントを整理します。
制作費用と相場の目安
BtoB動画の費用は、目的やクオリティによって大きく変動します。簡単な編集動画であれば10〜30万円程度、撮影やアニメーションを伴う商品紹介・ブランディング動画は30〜150万円前後が一般的です。
企業のブランドを訴求するような採用・企業紹介動画では、演出や撮影規模に応じて100万円以上になることもあります。
内製と外注のどちらを選ぶべきか
内製は、スピードとコストを重視する場合に向いています。社内で編集スキルや機材があるなら、操作説明・社内教育・SNS用短尺動画などは十分対応可能です。
一方で、外注はクオリティや信頼性を重視する場合におすすめです。ブランディング・採用・展示会向け動画など、企業の印象に直結するものは、プロの構成・撮影・編集によって完成度が大きく向上します。
BtoB向け動画コンテンツの展望
今後のBtoBマーケティングでは、AIや自動化技術の進化によって動画コンテンツの活用がさらに広がると考えられます。AIを活用したパーソナライズ動画では、視聴者の業界や役職に合わせて最適なメッセージを自動生成できるようになり、より精度の高い情報提供とリード育成が可能になります。
また、自動編集やシーン選定といった技術の発展により、制作コストと時間が大幅に削減される見込みです。これにより、企業はより頻繁に動画を配信でき、マーケティング活動のスピードと柔軟性が高まります。
こうした技術革新を取り入れることで、BtoB企業は今後さらに効果的に動画を活用し、顧客ごとに最適化されたアプローチを実現していくでしょう。
おわりに
今回は、BtoBマーケティングにおける動画コンテンツの活用についてご紹介しました。これまで、BtoBマーケティングではあまり取り入れられることのなかった動画コンテンツでしたが、最近では積極的に活用されています。
動画コンテンツを最大限に生かして、見込み顧客の獲得、育成や、企業イメージのアップへとつなげましょう。
【関連記事】